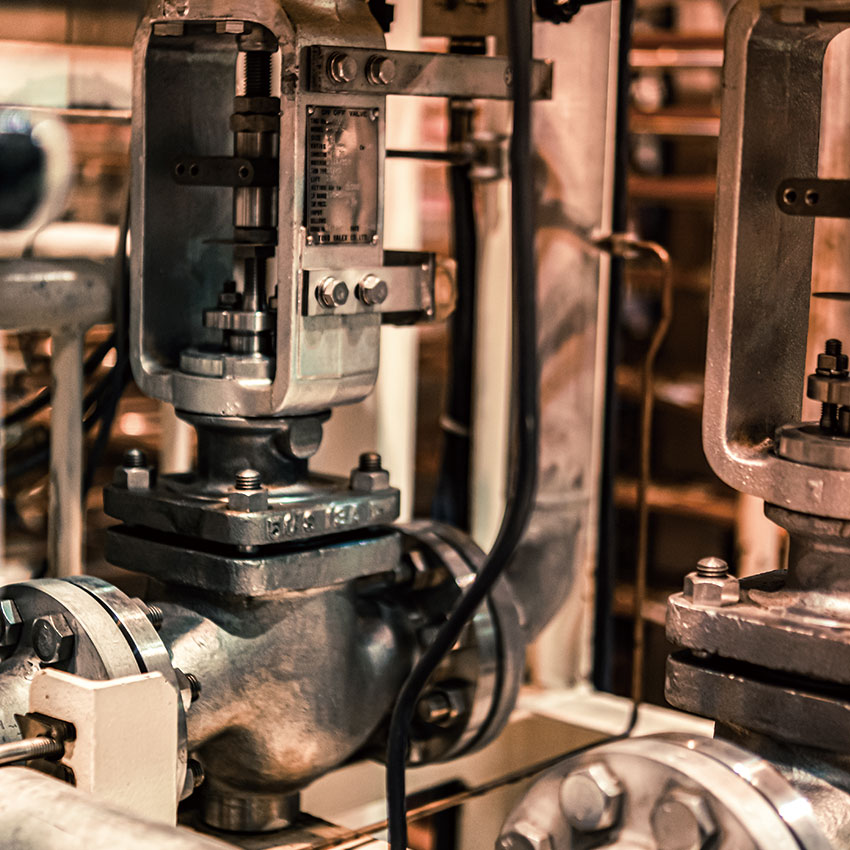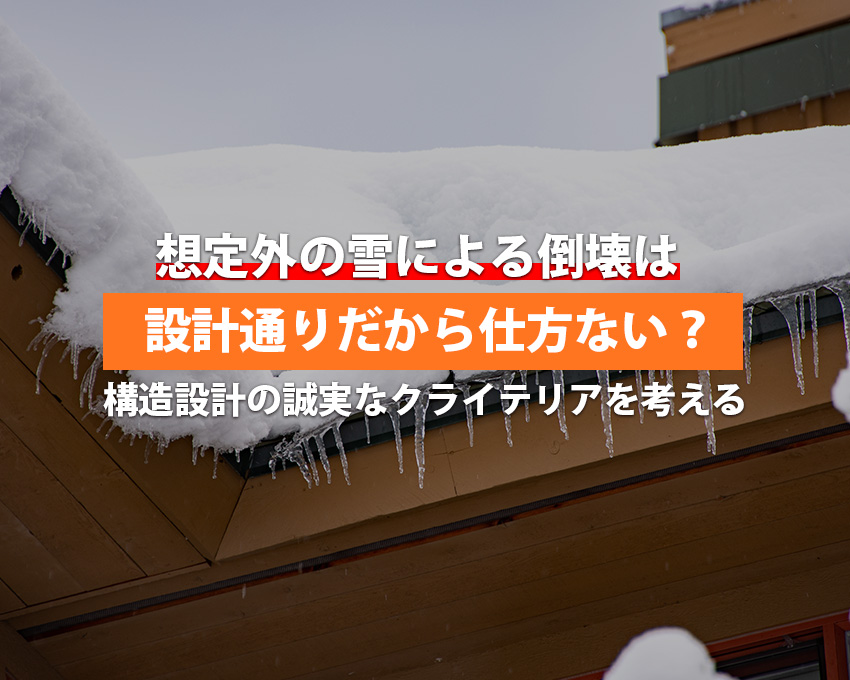
近年、これまでの統計を塗り替える「ドカ雪」が各地を襲っています。
建物が倒壊した際、「設計通り(建築基準法通り)だから仕方ない」と突き放すのは、計算書の上では正論でも、構造の専門家としてはあまりに不誠実です。
構造設計者の仕事は、単に図面を役所に通すことではなく、その建物が建ち続けることに責任を持つことです。
施主の資産と事業を守るために、不都合なリスクも隠さず共有し、納得感のある「設計条件(クライテリア)」をともに導き出す必要があります。
本記事では、異常気象時代に求められる構造設計者の誠実なあり方について考えます。
豪雪地ですら耐えられない。今、日本中の屋根で起きている現実
異常気象は、もはや「想定外」という言葉では片付けられないフェーズに入っています。
新潟県の雪害事例
2026年2月3日の朝、豪雪地として知られる新潟県で、記録的な大雪により建物の倒壊が相次ぎました。
新潟県柏崎市で1m50cmの雪が積もった車庫が倒壊し、下敷きとなった男性が心肺停止となりました。
また、長岡市では2日の夜に商店街のアーケードが雪の重みにより崩落しました。
(https://newsdig.tbs.co.jp/articles/bsn/2443187)
北海道小樽市の雪害事例
2026年2月12日、小樽市の大型商業施設「ウイングベイ小樽」で、雪庇が2階屋外にある歩行者通路の屋根に落下し、雪の重みにより長さ6~7m、幅2mほどが崩落しました。
(https://newsdig.tbs.co.jp/articles/hbc/2462689)
北海道名寄市の雪害事例
2023年2月18日には積雪対策が万全なはずの豪雪エリア名寄市で、築わずか5~6年のコンビニの天井が崩落したニュースが世間を騒がせました。
警察によれば、店舗では朝からミシミシと建物のきしむ音がしていたそうです。
当時の積雪は1mを超えていました。
詳しい原因は報道されていませんが、北海道科学大学の千葉隆弘教授は「”稀なケースですね。健全な状態であれば、まず壊れない。(中略)同じ構造形式の店舗に対し、点検していく必要があると思う。“」とコメントしています。
(https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/339268?page=3)
このように、雪に慣れているはずの地域の建物ですら、近年の急激な積雪に耐えられないケースが増えています。
当然、気象の変化に合わせて建築基準法も改正されています。
近年では、平成26年(2014年)の非多雪地域の災害を受け、平成31年(2019年)に積雪荷重が改定されました。
(https://www.bousai.go.jp/kaigirep/houkokusho/hukkousesaku/saigaitaiou/pdf/02jirei5.pdf)
しかし、多雪地域でさえ予想できない量のドカ雪が降り、これまで雪が少なかったエリアで急な積雪が増えるといった現象は、今後さらに増えるのではないかと懸念しています。
構造計算における荷重の「長期」「短期」とは?
長期荷重は建物に常にかかる荷重(自重、積載荷重など)で、短期荷重は地震力、風圧力、積雪荷重のように一時的・短時間に作用する荷重を指します。
積雪荷重の取り扱いは地域によって異なります。
- 多雪地域:長期荷重に考慮
- 非多雪地域:短期荷重に考慮
- 地域的な条例:(例)北海道条例では多雪区域外も長期荷重に考慮
長期荷重とは(重力など)
建物の自重のように常に作用し続ける荷重のこと。材料の劣化や変形を考慮し、比較的余裕のある設計がなされます。
短期荷重とは(地震・風など)
地震発生の数分や暴風の数時間など、一瞬だけ作用する荷重。たまにしか起きない事態であれば、多少大きな負荷(短期許容応力度)まで許容してもよいと考えられています。
材料やかかる力によって倍率は変わりますが、短期許容応力度は長期許容応力度(常時作用する力に対する値)の1.5倍〜2倍程度と、長期より大きい許容値になります。
豪雪地帯などは、常に余裕がある「長期荷重」で設計するのに対し、通常、本州の積雪の少ないと言われている地域は「短期荷重」として扱われます。
これは雪の重みに対して「地震や風に耐えるときと同じ瞬間的にかかる力」に対して耐えることを前提に計算されていることになります。
「想定外の積雪が与える構造への影響」について、短期荷重で設計された建物に大量の雪が降り積もったとしたらどうなるのか、と仮定して説明します。
「たったそれだけで?」想定外が致命傷になる構造の限界
建物は、「想定より荷重が少し重くなった」だけで壊れる可能性があります。
例えば、30cmの積雪を想定して設計された建物に、ドカ雪で50cm積もったとします。
設計者でない方は「たった20cmオーバーしただけでは何も影響しない」と思われるかもしれません。
しかし、前述の通り「短期荷重」としての設計では、材料が耐えられる限界(降伏点)までの余力は、わずか1割程度しかありません。
30cm想定に対して50cmの雪が乗るということは、設計上の負荷を約1.6倍も上回ることを意味します。
1.1倍程度の余力しか持たせていない構造体にとって、1.6倍の荷重はもはや「許容範囲」を遥かに超えています。
一瞬の地震や風なら耐えられたとしても、雪の場合はその過酷な負荷が続き、建物の骨組みをじわじわと押し潰していきます。
積雪荷重の取り扱い|積雪深と比重
先述の例はわかりやすさを優先してかなり単純化した例ですが、実際には積雪深と比重の考え方が欠かせません。
冒頭に紹介した平成26年(2014 年)の非多雪地域の被害事例は、実際の原因は降雪量そのものではなく、後に降った雨によって雪が大量の水分を含んだために想定以上の重さに達したことにより起こりました。
北海道、青森県、山形県、新潟県、富山県などの多雪地域に共通する現象として、数か月を通し、積もっては解けを繰り返すと、下層の雪は圧が高くなりどんどんと重くなります。
また、東北、特に日本海側では内陸に比べて湿った重い雪が降ります。
雪の比重は概ね建築基準法で統一されているものの、このように地域によって比重がかなり異なるため、一概に積雪深だけで測れないという難しさがあります。
「計算」の前に「クライテリア(設計条件)」の合意が大切
とはいえ、建物が壊れた後で、設計者が「設計図通りなのだから、異常気象が悪い」と責任を転嫁するのは、プロとしての思考停止でしかありません。
どのような理由があろうとも、結果として施主の資産を守れなかったという事実には変わりないからです。
コストとリスクのバランスを施主任せにせず、「どのくらいのハードル(クライテリア)を設定すべきか」をプロとして事前に提示し、合意形成する。
このプロセスこそが、設計者の本質と言えるのではないでしょうか。
数字には表れない「設計者の配慮」が建物寿命を延ばす
自然現象を100%予測した設計というのは、不可能です。
例えば、降雪による庇(ひさし)の被害事例はよく見られますが、これは風向きや建物の形状によってできる雪の吹きだまりが原因で発生するケースがほとんどです。
実際には、気象庁が発表している積雪よりも多い雪が庇に集中して積もります。
また、下階の屋根が上階の壁よりも外側にせり出している(セットバック)の建物では、上階から下階の屋根へ雪が叩きつけるように落ちます。
これは積雪の重さよりはるかに大きな衝撃を与えます。
また、積雪の不均衡により、梁が折れたり歪んだりすることがあります。
これらは、積雪荷重を割り増しする程度の対応では難しい場合が多いです。
では、建物全体の積雪荷重を3倍にすればよいのかというと、経済的合理性が無くなってしまいます。
庇は雪の重みで壊れやすいため、国の告示による計算ルールで、通常よりも大きい荷重を見込むことが義務付けられています。
実質的に2倍程度の安全率を持って設計されているはずですが、それでも壊れてしまう。
それほど庇の積雪は過酷なのです。
しかし、100%の予測は不可能だとしても、構造のプロであれば積雪に関して次のようなことを考慮した設計をする必要があるでしょう。
- 建物形状から予測される「雪だまり(偏積荷重)」への局所的な補強
- 雪庇(せっぴ)やつららによる二次被害、軒先の折れを防ぐための細部の検討
これらは法規で強制されるものではありませんが、当然配慮すべきです。
設計者が現場の状況をどれだけリアルに想像できるかという「配慮」が、設計の差となって表れます。
まとめ|「想定外」が事業を止める前にリスクを語れる設計者を選ぶ時代へ
今回ご紹介したドカ雪による倒壊・損傷事例は住宅やコンビニでしたが、雪の重みは建物の用途を選びません。
特に、広い屋根を持つ中大規模施設や物流施設であれば、その荷重は住宅の比ではなく、万が一の崩落が事業に与えるダメージもまた、桁違いに甚大です。
異常気象が日常化した今、構造設計者は単に法規上の数字を合わせるだけではなく、設計のリスクとクライテリアの設定まで踏み込んでお客様とともに考えていくことが必要ではないでしょうか。
私たちさくら構造はこれからも、数字の先にある「お客様の安心」と誠実に向き合い続けます。
- システム建築の「合理性」と在来建築の「自由度」を両立
- 工事業者を自由に選ぶことができ、値引き交渉を有利にできる
- 基礎工法を配慮した上部構造への対応が可能
多雪地域のコスト削減事例